「それにしても、またこうして会えるなんて思ってませんでしたよ」
お昼休み。学食は多くの生徒達でごった返しています。
向かい合って座った稔くんは、自前のお弁当です。
小さなおにぎりが三つに、から揚げとたこさんウインナー、卵焼き、生野菜が少々というオーソドックスな組み合わせ。
シンプルながらおいしそうです。これを自分で作ってきてるなんて、尊敬してしまいます。
一方、ぼくはお弁当組ではないので、去年もよく食べていたAランチ(三百円)。
ぼくとしてはすっかり食べ慣れた味で物珍しさもないのですが、稔くんは注文しているぼくとAランチを交互に見てから、ぼそっと呟きました。
「ブルジョワ階層……」
なんだかよくわかりませんが、稔くんも苦労しているようです。
「恭くんのお父さんとお母さんってどんな仕事してるの?」
「音楽家ですよ。父がヴァイオリニストで、母がピアニストです」
「へえ、なんかすごいなあ。恭くんも何か楽器出来るの?」
「ぼくはトランペットですね。吹奏楽部にも入ってますよ。まだまだ未熟者ですけどね」
本当は、お母様はぼくにピアノを習ってほしかったみたいですけど……。
そうとわかっていながらトランペットを選んだのは、親に対するぼくの小さな反抗心だったのかもしれません。
「恭くんはすごいね。僕なんて特別何かが出来るってわけじゃないからさ」
「そんなことありません。稔くんは、ぼくを助けてくれたじゃないですか」
誰にも助けてもらえないと思い込んでいたところに差し伸べられた救いの手。
あのときの感動は今でも忘れられません。
「本当にありがとうございます」
「大したことじゃないよ。それに、あのときほどの力はもうないんだ」
「そうなんですか?」
「今でも見えることは見えるんだけどね。少しずつ弱くなってっちゃったな」
力が弱くなる? そういうこともあるのでしょうか。
ぼくは物心ついたときからずっと変化がないので、特にそういった実感はありません。
ただ、意識して見ないようにすることは出来るようになりました。
そのおかげか、子供の頃のように襲われることはなくなりました。
どうやらアレは、自分たちを見ることの出来る人に寄っていくことが多いのでは、と推測出来ます。
「あのときだけなぜかすごく力が出せたんだよなあ。なんでだろう」
稔くんの言葉に、ふと思いつくものがありました。
「もしかして、指輪のせいでしょうか……?」
「指輪……? ああ、そういえば、そんなの拾ってたような気も……」
「稔くんに助けてもらった後、透明な玉のついた指輪を拾ったんです。それに特別な力があったんじゃないでしょうか」
当時拾ったときに、何か引き込まれるものを感じましたし。
ただの指輪とは考えにくい。そんな直感がありました。
でも、そういえばあの指輪はどこにいってしまったんでしょう?
誰かにあげたような覚えがあるのですが、記憶が曖昧で思い出すことが出来ません。
随分と前のことですから、仕方ないといえば仕方ないのですが……。
「何にしても、こうしてまた出会ったのも何かの縁です。今後ともよろしくお願いします。お近づきの印に、これをどうぞ」
Aランチのミックスフライ、その内のエビフライをそっと稔くんに差し出しました。
途端に稔くんの顔がぱあっと明るくなって、
「い、いいの!?」
「はい。どうぞ召し上がってください」
「……恭くん。君は女神だったんだね」
「お、大袈裟ですよ」
ぼくは男ですから、女神という表現は適切とは言い難いです。
それでも、そう言ってもらえたことが嬉しくて、照れ隠しにパック牛乳のストローをぱくりとくわえます。
女の子扱いされること、結構ありましたからね……。
「あら、恭くんじゃありませんか」
その呼びかけに振り向くと、トレイを持った智香お姉ちゃんが立っていました。
「早速新しいクラスの子と仲良くなったんですね」
「あ、初めまして。桜井・稔です」
「ご丁寧にどうも。私は樋口・智香といいます」
にっこりと笑顔になって、智香お姉ちゃんは小さくお辞儀をしました。
稔くんは少し考える仕草をしてから、小さく口を開きます。
「樋口? もしかして……」
「はい、ぼくのお姉ちゃんです」
「いいなあ恭くんは。こんなに綺麗で優しそうなお姉さんがいて」
「ふふ、ありがとう稔くん。でも、あんまり優しくないお姉さんもいるんですよ」
「……それは一体誰のことを言ってるわけ?」
にこやかな笑顔を浮かべる智香お姉ちゃんの背後から、こめかみをひくつかせながら立っていたのは、恵子お姉ちゃんでした。
怒りのオーラが目に見えるようで、周りを歩いていた人達がそっと離れていきます。
「まったく、人がちょっと何頼むか迷ってる間に好き勝手言って。あたしの厳しさは優しさなのよ。いわば愛の鞭ってやつ。恭、あんたならわかってるでしょ?」
「う、うーん、それはどうでしょう……」
「……そういえば、今朝面白いものを見たような気が」
「恵子お姉ちゃんはとっても優しいですね! あ、向こうの席が空いたみたいですよ?」
「あら、本当ね。いつまでも突っ立ってるのもなんだし、行きましょ智香姉」
促して歩いていこうとする間際、恵子お姉ちゃんは稔くんに鋭い視線を向けました。
「あんた、名前は?」
「あ、桜井・稔です」
「桜井、ね。恭と仲良くするなら、あたしのご機嫌には気をつけることね。ああ、あたしは恵子って名前だから、気軽に恵子様って呼ぶといいわ。それじゃね」
好き勝手言うだけ言って、恵子お姉ちゃんはのっしのっしと歩いていきました。
智香お姉ちゃんも、ぼくらに軽く会釈してから、恵子お姉ちゃんにくっついていきます。
まるで嵐が過ぎ去ったかのような落ち着いた空気が戻ってきて、稔くんはほっとしたように溜息をつきました。
「こ、怖かった……」
「ご、ごめんなさい稔くん。恵子お姉ちゃんも悪い人じゃないんです。ちょっと気が強いだけで」
「それはわかるけど、ああいう性格はちょっと苦手かも」
言いながら、苦笑いする稔くん。
確かに、ぼくも恵子お姉ちゃんのちょっと意地悪なところは、得意ではないですね。
「恵子お姉ちゃんも、いつもあんな感じというわけではありませんから。良かったら今度家に遊びにきてくださいね」
「ありがとう。僕の方も今度招待するね!」
「はい、楽しみにしてますね」
ぼくらは和やかな雰囲気の中、ゆっくりと昼食を楽しみました。
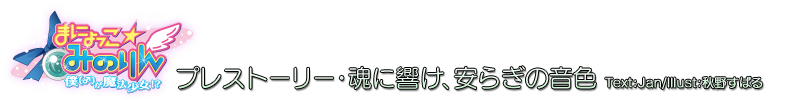
■05